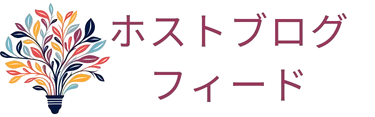これがあなたのためのパズルです。無数の淡水の川や小川から水を受け取っているにもかかわらず、海はどのようにして塩辛いままなのでしょうか?
今日、私たちはこの謎をきっぱりと解き明かし、海が塩を蓄積するさまざまな方法をすべて明らかにしています。
天候の変化が、海の塩分濃度を維持するバランスにどのような影響を与えるのかを見ていきます。
また、この過酷な環境で生き残るために、海洋植物や動物に見られるユニークな変化も発見できます。
世界にはいくつの海がありますか?

人々が七つの海と言うとき、実際には世界の海を指しています。
これらには、北極海、北大西洋、南大西洋、インド、北太平洋、南太平洋、南極海が含まれます。
しかし、海は実際にはより多様な水域をカバーする包括的な用語です。まず、海が実際に何であるかを定義することから始めましょう。
一言で言えば、海は塩辛い水の塊です。「海」というフレーズは海を指しますが、特定の海はカスピ海のような小さな海域または内陸の水域です。
今では、この定義に適合する海が世界中に50以上あることは容易に理解できます。しかし、興味深い事実は、サイズに関係なく、それらすべてが接続され、地球の海を形成しているということです。
これをさらに単純化し、サイズに基づいて海と海を区別する人もいます。これらの基準では、海は地球上の主要な大きな水域を指し、海は小さいです。
海が塩辛いのはなぜですか?

きれいな雨水はわずかに酸性で、pHは5.0〜5.5の範囲です。空気に他の不純物が含まれている場合、pHはさらに4.0まで低下する可能性があります。
この酸性度は有害ではありませんが、接触する岩石や土壌から一部のミネラルを溶かすのに十分です。
イオンと呼ばれるこれらの溶解ミネラルには、ナトリウムや塩素などの物質が含まれています。雨水が流れると、これらのイオンが集まり、塩分が生成されます。
この塩分を含んだ水は川に流れ込み、やがて海にたどり着き、年間約40億トンの塩分を海に運んでいます。
しかし、これは新たな疑問を提起します。川が塩を海に運んでいるのなら、なぜ塩辛くないのですか?
まあ、雨が降るたびに、存在する塩分を含め、川の水が希釈されます。しかし、この水を他の場所に送っているため、塩分濃度は増加しません。
一方、海は常にわずかに塩辛い水で満たされており、行き場がないため、時間の経過とともに蓄積され、集中します。
塩が海に入る別の方法は、海底からです。海水は海底の割れ目に浸透し、マグマによって加熱されます。この反応により、ミネラル塩が海に放出されます。
生物は海水でどのように生き残るのですか?

科学的には、海水のような塩辛い溶液は、浸透と呼ばれるプロセスを通じて自然に水を外側に引き込みます。水の損失を放置すると、海の生き物でさえ脱水状態になる可能性があります。
ありがたいことに、海に生息する242,000種以上は、水を節約するための特別な適応を持っています。
たとえば、アホウドリのような一部の海鳥は、海水を飲んで塩分を分離することを可能にする特別な腺を持っています。
魚に関しては、えらと腎臓が塩分をろ過するのに役立ちます。
興味深いことに、サメは他の魚のように水を飲むのではなく、鰓から水を吸収します。その後、消化器系は、滑り落ちる余分な塩分を取り除きます。
ほとんどの海洋植物は、物事を少し違った方法で扱います。塩分子を管理可能なイオンに分割するものもあれば、呼吸器プロセスを通じて塩を除去するものもあります。
なぜ一部の海は他の海よりも塩辛いのですか?

海の平均塩分濃度は35ppm、つまり3.5%ですが、これは海によって大きく異なります。
降水量(雨、雪など)、温度、蒸発速度によって、水域がどれだけ塩辛くなるかが決まる場合があります。
平均して、赤道や極に近い海は、中緯度付近の海よりも塩分が少ないです。
世界で最も塩分の多い海の1つは死海で、約35.1%の塩分が含まれています。平均塩分濃度の約10倍で、通常の海洋生物を維持するには塩分が多すぎます。
死海の最もユニークな特徴の1つは、塩分濃度が高いため、水が通常よりもはるかに密度が高いことです。したがって、水に入ると、沈むのではなく、上に浮かぶだけです。
一方、エストニアに近いバルト海は、約0.7〜0.8%と最も塩分が少ないです。
バルト海の塩分濃度が低いのは、主に、バルト海に供給する川や小川の数に比べて蒸発レベルが非常に低いためです。
そのため、塩は川や小川から海に運ばれます。この塩分は行き場を失い、時間の経過とともに濃縮され、海が塩辛くなります。
ただし、特定の海に含まれる塩の量は、天候とその場所によって異なる場合があります。
海水は塩分が多すぎるため飲むことができませんが、それでも特定の動物や植物にとっては住処となっています。これらの種は、海の塩に対処するための特別な適応を持っています。